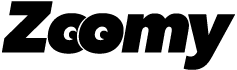バークシャーのチャーリー・マンガー氏は、「誤った判断をしてしまう人間の心理」について、1995年にハーバード大学で行われ講演「The Psychology of Human Misjudgment(人間の誤判断の心理学)」で語っています。
この講演は、人間が陥りやすい思考の偏りやバイアスを25の心理的バイアスについて解説し、これらが意思決定にどのような影響を及ぼすかを探求しています。これらのバイアスには、次のようなものがあります。
・報酬と罰の超反応傾向
人間は報酬を得るため、または罰を避けるために強く反応します。この傾向は、行動を動機づける強力な要因となりますが、過度に反応することで判断を誤る可能性があります。例えば、短期的な報酬を追求するあまり、長期的な利益を犠牲にする決定を下すことがあります。
・好意/愛情傾向
人間は、好意や愛情を抱く対象に対して、その欠点を過小評価し、長所を過大評価する傾向があります。この傾向により、信頼しすぎたり、批判的な視点を欠いたりすることがあります。例えば、親しい友人や家族の提案を無条件に受け入れることで、客観的な判断ができなくなることがあります。
・嫌悪/憎悪傾向
逆に、嫌悪や憎悪の感情を抱く対象に対して、その長所を無視し、欠点を過大評価する傾向があります。このため、偏見や差別的な行動をとるリスクが高まります。例えば、特定の人物やグループに対する否定的な感情が、合理的な判断を妨げることがあります。
・疑念回避傾向
人間は、不確実性や疑念を避ける傾向があります。このため、明確な答えや確信を求め、複雑な問題を単純化したり、早急に結論を出したりすることがあります。例えば、情報が不十分な状況でも、直感や初期の印象に基づいて決定を下すことがあります。
・一貫性回避傾向
人間は、一貫性のない行動や思考を避ける傾向があります。一度決定や信念を持つと、それに固執し、矛盾を避けるために新しい情報や意見を無視することがあります。例えば、過去の投資判断が間違っていたと認めることを避け、損失を拡大させることがあります。
・好奇心傾向
人間は、新しい情報や経験を求める好奇心を持っています。この傾向は学習や成長を促進しますが、過度な好奇心は注意散漫やリスクの過小評価を招くことがあります。例えば、新しい投資機会に飛びつくあまり、十分な調査を怠ることがあります。
・カント的公平性傾向
人間は、公平性や正義を重視する傾向があります。これは、倫理的な行動や社会的調和を促進しますが、過度に公平性を追求することで、効率性や成果を損なうことがあります。例えば、全員に平等な報酬を与えることで、優秀な人材のモチベーションを下げることがあります。
・嫉妬/羨望傾向
人間は、他者の成功や富を羨ましく思う傾向があります。この感情は、競争心を刺激する一方で、不正行為や非倫理的な行動を誘発するリスクがあります。例えば、他者の成功を妨げるために、意図的に情報を隠すことがあります。
・返報性傾向
人間は、他者からの行為に対して同様の行為で応じる傾向があります。これは社会的な絆を強化しますが、悪意のある人々に利用される可能性もあります。例えば、小さな贈り物を受け取ったことで、大きな要求を受け入れてしまうことがあります。
・単なる連合からの影響傾向
人間は、物事や人を関連付けて判断する傾向があります。このため、無関係な要素が意思決定に影響を及ぼすことがあります。例えば、製品の品質とは無関係な有名人の推薦に影響されて購入を決定することがあります。
・単純な心理的否認
「私が信じたくないものは、存在しないことにする」というのが心理的否認の本質だ。人間は、自分にとって都合の悪い現実を直視するのを避ける。例えば、タバコを吸っている人が「肺がんなんて自分には関係ない」と考えるのがこれに当たる。
多くの人は、自分が買った株が暴落したとき、「これは一時的な下げだ」と言い聞かせる。しかし、実際には企業の業績が悪化し、本当に価値が下がっている可能性がある。現実を否認するのは楽だが、結果的に大きな損失を招くことになる。
・過度の自己評価傾向
人間は「自分は平均以上」と思い込む生き物だ。これは心理学では「優越の錯覚」と呼ばれる。面白いことに、大半の人が自分を「運転がうまい」と思っているが、統計的にそれは不可能だ。
多くの個人投資家が「私は市場平均を上回れる」と信じている。プロのファンドマネージャーでさえ、市場平均を超えるのは難しいのに、個人投資家がそう思い込むのは危険だ。自己評価を誤ると、過剰なリスクを取る原因になる。
・過度の楽観主義傾向
「すべてうまくいく」と思い込むのが楽観主義の落とし穴だ。人間は、自分に都合のいいシナリオばかりを考え、リスクを過小評価する。例えば、宝くじを買う人は「自分は当たる」と考えるが、実際の確率を考えれば当たる可能性はほぼゼロに近い。
バブルが起こるたびに、人々は「今回は違う」と言って株を買い続ける。しかし、歴史は繰り返す。楽観的すぎると、大きな下落に備えられず、財産を失うことになる。
・喪失超反応傾向
人間は「損失の痛み」を「利益の喜び」よりも強く感じる。つまり、100ドルを得たときの喜びよりも、100ドルを失ったときの痛みのほうが大きい。
株が下がったとき、人々は「損切り」をためらう。「今売ったら損が確定してしまう」と考えるが、実際には悪い銘柄を長く持ち続けることが、より大きな損失を生む。損失を受け入れる勇気を持つことが重要だ。
・社会的証明傾向
「みんながやっているから、自分もやる」。これは原始時代から続く人間の本能だ。集団で行動することで、生存確率を上げてきた。しかし、現代社会ではこの本能が裏目に出ることが多い。
「みんなが買っているから、この株は間違いない!」と思って高値で飛びつく。結果、バブル崩壊時に大損することになる。成功する投資家は、群衆と逆の行動を取る勇気を持っている。
・対比誤反応傾向
「これは安い!」と思ったことはないだろうか?しかし、それは本当に安いのだろうか?それとも、単に比較対象が高かっただけなのか?これは「対比誤反応傾向」と呼ばれるもので、人間は物事を絶対的な基準ではなく、相対的な比較で判断してしまう。
例えば、ある株が1年間で50%上昇したとする。その後20%下落したとき、多くの人は「まだ30%も上がっている」と楽観視する。しかし、過去の上昇を基準に判断するのではなく、その企業の本来の価値と比べるべきだ。
市場の狂気に流されず、冷静に考えなければならない。
・ストレス影響傾向
ストレスがかかると、人間は冷静な判断ができなくなる。進化の過程で、ストレスを感じたら「すぐに行動する」ことが生存戦略として有効だったからだ。しかし、現代ではこれはしばしば逆効果になる。
株式市場が急落すると、多くの投資家はパニックに陥り、損切りしてしまう。しかし、長期的な視点では、パニック時こそ絶好の買い場だったりする。ウォーレン・バフェットが「恐怖の時に買い、貪欲の時に売れ」と言ったのは、この心理を逆手に取るためだ。
・利用可能性誤重み付け傾向
人間は、記憶に残りやすい情報を過大評価する。これは「最近のニュースや目立つ情報ほど重要だと思い込む」バイアスだ。例えば、メディアが「新興企業のAI技術が革命を起こす!」と騒ぎ立てると、多くの投資家はその株を買いたくなる。
しかし、冷静に見ると、その企業の業績や技術は実際にはそこまで革新的でないことが多い。流行に流されず、本質を見極める目が必要だ。
・使わなければ失う傾向
「今使わないと損する」と考えて、つい無駄なことに時間やお金を使ってしまう。これは、筋肉や言語能力のように「使わないと本当に失われるもの」には有効だが、すべてに当てはまるわけではない。
例えば、企業が「手元資金を持っていても意味がないから」と言って、不必要な買収や設備投資を行うことがある。しかし、現金を無駄に使うより、より良い投資機会を待つ方が合理的な場合も多い。キャッシュポジションを保つことも、立派な戦略なのだ。
・薬物誤影響傾向
薬物は、人間の認知や判断を歪める。アルコールやドラッグの影響だけでなく、カフェインや糖分の摂取も思考に影響を及ぼす。これは、決して軽視してはいけない。
例えば、株式トレーダーの中には、集中力を高めるためにカフェインやエナジードリンクを大量に摂取する者がいる。しかし、これらは短期的な覚醒効果はあっても、長期的には判断を鈍らせる可能性がある。
また、アルコールの影響で冷静な判断ができず、大胆な賭けに出るケースもある。投資においては、常にクリアな頭を保つことが重要だ。
・老化誤影響傾向
「年を取ると賢くなる」と思ったことはないだろうか。残念ながら、人間の脳は加齢とともに認知能力が低下する。記憶力、判断力、柔軟性が衰え、過去の経験に過度に依存する傾向が強くなる。
長年市場で成功してきた投資家が、時代の変化を認めずに「昔はこうだったから今も同じはずだ」と考え、大きな失敗をすることがある。たとえば、ウォーレン・バフェットでさえ、テクノロジー株への投資に慎重すぎた時期があった。
過去の成功パターンが、未来でも通用するとは限らない。時代に適応する柔軟性が必要だ。
・権威誤影響傾向
「偉い人が言っているから正しい」と思い込むのは間違いだ。人間は、肩書きや権威を持つ人物の意見に影響されやすい。これは社会の秩序を保つ上では有益だが、判断を誤る原因にもなる。
例えば、有名な経済学者や投資家が「この株は買いだ!」と言ったからといって、その意見が必ず正しいとは限らない。2008年の金融危機の前には、多くの「専門家」が「住宅市場は安全だ」と言っていたが、それが誤りだったことは歴史が証明している。
大事なのは、誰が言っているかではなく、何が言われているかを見極めることだ。
・無駄話傾向
どうでもいい話が好きな人ほど、人生を無駄にする。人間は、本質的に意味のない会話を楽しむ生き物だ。ゴシップや関係のない情報に気を取られ、重要なことを見逃してしまう。
金融ニュースを見ていると、短期的な値動きや憶測ばかり報じられる。「FRBの発言で市場が乱高下!」、「著名投資家が○○の株を購入!」これらの情報は面白いが、長期的な投資判断にはほとんど役に立たない。
投資で成功するには、余計なノイズを排除し、本当に重要な情報だけに集中することが大事だ。
・理由尊重傾向
「理由がついていれば納得する」のは、人間の盲点だ。たとえその理由が薄っぺらいものでも、「理由がある」だけで納得してしまう心理がある。研究でも、「理由がある」ほうが人は説得されやすいことが証明されている。
株のアナリストが「この企業の成長率は素晴らしい」と言いながら、「なぜ?」という問いに対して納得のいく答えを出せないことがある。投資判断の際は、「その理由は本当に論理的か?」を常にチェックすることが重要。
「みんなが買っている」とか、「CEOがカリスマだから」といった表面的な理由に惑わされるな。
・ロラパルーザ傾向
複数のバイアスが組み合わさると、人間はさらにバカな決断をする。マンガーが最も重視する心理バイアスの1つが、この「ロラパルーザ効果」だ。1つのバイアスだけではなく、複数のバイアスが同時に働くことで、意思決定が劇的に歪められる。
例えば、バブルが発生するときには、社会的証明(みんなが買っている)、過度の楽観主義(価格は上がり続ける)、喪失超反応(今買わなければ乗り遅れる)、権威誤影響(著名投資家が推奨)」といった複数のバイアスが組み合わさる。その結果、人々は冷静な判断を失い、割高な株を買ってしまう。
2000年のITバブル、2008年の住宅バブル…歴史は繰り返す。「ロラパルーザ効果」が働くと、人々は集団で愚かな行動をとる。
チャーリー・マンガーは、これらのバイアスが組み合わさることで「ロラパルーザ効果」と呼ばれる強力な影響を生み出し、人々が非合理的な行動を取る原因となると指摘しています。
マンガーは、これらの心理的傾向を理解し、認識することで、誤った判断を避け、より合理的な意思決定が可能になると強調しています。彼の洞察は、投資のみならず、日常生活やビジネスにおける意思決定にも深い影響を与えています。
これらの心理的傾向を理解し、認識することで、より良い意思決定が可能になります。