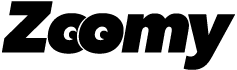ジョン・テンプルトン卿は、「伝説のバリュー投資家」として世界に名を馳せました。彼が大切にしていたのは、単なる安値買いではありません。本源的価値(企業の本当の価値)を見極め、その価値から大幅に割安なものを慎重に選ぶという、極めて規律ある投資哲学でした。
この記事では、テンプルトン卿の考え方を、わかりやすく解説していきます。
掘り出し物とは「本当の価値の8割引き」
テンプルトン卿は、掘り出し物とは、本源的価値(本来の価値)より80%も安いものだと考えていました。
つまり、企業の本来の価値を100とするなら、株価が20以下に落ち込んでいるような状態。単に「安いから買う」のではなく、本質的な価値を冷静に推定したうえで、その大幅ディスカウントを狙うのが彼のスタイルだったのです。
この考え方は投資だけでなく、彼の生活にも表れていました。たとえば、テンプルトン卿はソファーを95%引きで購入したことがあり、生活全体でも「本質的価値に対してどれだけ得か」を常に意識していたのです。
新しい投資アイデアは「現在保有株より50%以上魅力的」でなければならない
テンプルトン卿のファンドでは、新しい投資対象を選ぶ際に一つの基準がありました。それは、現在保有している銘柄と比べて、少なくとも50%以上アップサイド(上昇余地)が大きくなければならないというルールです。
そして、この見込み上昇幅を実現するための想定期間は基本5年。さらに、より大きなディスカウント(割安度)があれば、10年までじっくり待つことも選択肢にしていました。
この考え方に基づき、内部収益率(IRR)もしっかり計算し、リターンとリスクを見極めていました。
具体例:アルセロール・ミッタルとアリババ
テンプルトン卿のアプローチは、単なる理論ではありません。実際に彼のファンドが成功した具体例も見てみましょう。
鉄鋼大手アルセロール・ミッタルの場合
・2012~2013年、ヨーロッパの債務危機後、鉄鋼メーカー「アルセロール・ミッタル」の株価は、簿価の10~25%程度まで暴落しました。
・このとき、300~400%の上昇可能性があると判断し、大幅に仕込んでいます。
・リターンを得るまでの期間にも柔軟性を持たせ、焦らず待ったのが特徴です。
アリババの場合
・一方、アリババはIPO直後に株価が高騰しましたが、その後6~12か月で30~50%の急落を経験。
・これにより、成長性を加味したときに200~300%の上昇シナリオが成立したため、投資対象となりました。
このように、一時的な悪材料や市場心理の崩れをチャンスと捉え、本源的価値と比較して明確なディスカウントがあるものだけを厳選していたのです。
成功も失敗も、すべてプロセスの一部
もちろん、全ての投資が成功したわけではありません。とくに、アルセロール・ミッタルのような「景気循環に左右されやすい企業」への投資は、タイミングを見て売却する必要がありました。
しかし、アリババのように「長期的な成長が期待できる企業」では、リスクとバリュエーションが適切である限り、ずっと長く保有し続ける選択もしたのです。
つまり、テンプルトン卿の本質は、
–「ディスカウント率」と「成長余地」を冷静に見極め、
– それに応じて投資期間を柔軟に考える
という極めて合理的な姿勢にありました。
まとめ:「割安を買う」だけではない、テンプルトン卿の深さ
テンプルトン卿が示したのは、単に「安いものを買う」のではなく、「本源的な価値に対して、どれだけ信じられない価格で放置されているか」を見極める目を持つこと。
そして、冷静な分析と規律をもって、チャンスが来るまで待ち、来たら迷わず行動することでした。「掘り出し物とは、本源的価値より80%安いもの」このシンプルで力強い基準こそ、いまの私たちにも十分響く投資哲学だと言えるでしょう。