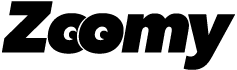以下は長期にわたるダウ平均株価チャート(1896年~2016年)は、経済、政治、世界的な出来事の視覚的な歴史を、指数のパフォーマンスとともに提供しており、特に市場が「停滞」していた期間、すなわち、回復する前に長期にわたる停滞や下落を経験した期間を強調しています。
主な停滞または横ばい市場ごとに、その時期に何が起こったのかを詳しく見てみましょう。
The history of the stock market: pic.twitter.com/VwHQeJMwH5
— Invest In Assets 📈 (@InvestInAssets) April 13, 2025
1906年~1925年(回復期間 19年)
この期間は、ダウ平均が1906年の高値を再び超えるまでに19年を要した、極めて長い停滞期でした。背景には複数の経済的・社会的ショックが重なり、市場が断続的な不安定さに見舞われたことが挙げられます。
【主な出来事】
・1907年のパニック(通称:Knickerbocker Panic)
大手信託会社の破綻により、銀行取り付け騒ぎが全米に波及。これが後の米連邦準備制度(FRB)設立(1913年)につながる。
・1913年:連邦所得税の導入(16条改正憲法)
それまでなかった恒常的な個人所得課税制度が導入され、富裕層・企業のキャッシュフローに大きな影響。
・第一次世界大戦(1914年~1918年)
欧州を中心に経済活動が停滞。アメリカは1917年に参戦。戦争関連支出によって一時的な需要増もあったが、市場には長期の不確実性が残った。
・1918年:スペイン風邪パンデミック
世界中で5,000万人以上の死者を出し、労働力不足と経済混乱を招いた。
・金本位制と物価変動の急変
戦争後のインフレを抑えるための金本位制復帰政策がデフレ圧力を招き、企業収益が悪化。
【市場動向】
・持続的な上昇が見られない不安定な相場が続く
市場は1906年のピーク後に崩れ、1925年になってようやく当時の高値水準を回復。複数のショックが重なり、長期投資家にとっては極めて厳しい時代だった。
・戦争・パンデミック・政策転換が株式市場の重荷に
政府の財政介入・新税制度・国際不安定要因(戦争・疫病)が複合的に作用し、市場は強いトレンドを持てなかった。
・企業活動とイノベーションは進行していたが、株式には反映されにくかった
自動車産業や航空技術など、成長分野はあったものの、金融市場全体としては沈滞ムードが支配。
1929年~1954年(回復期間:25年)
1929年、アメリカ経済の繁栄は突如として暗転します。「ブラックマンデー」から始まった株式市場の連鎖的な暴落は、歴史に残る「大恐慌」の幕開けとなり、ダウ平均株価はわずか数年でピークから90%近くも下落しました。
それは単なる市場の崩壊ではなく、経済・金融・雇用すべてが崩れていく国家的な災厄でした。銀行の連鎖破綻、失業率25%超、農村の困窮。市場の再起どころか、「資本主義そのもの」が揺らいでいた時代でもあります。
この深刻な危機に対し、1933年に大統領に就任したフランクリン・D・ルーズベルトは、ニューディール政策を掲げて公共事業や金融制度改革を断行。証券取引委員会(SEC)の創設や預金保険制度(FDIC)の導入など、資本市場の基盤を整える試みが進みました。
とはいえ、株式市場が本格的に回復軌道に乗るには、なお長い時間が必要でした。1937年には早くも景気後退が再発し、市場は再び低迷。本格的な転換点となったのは、第二次世界大戦(1939~1945年)による戦時経済でした。軍需産業の活性化、雇用の拡大、大規模な政府支出によってようやく実体経済が底上げされ、戦後の成長へとつながっていきます。
それでも1929年に記録したダウ平均の高値(約381ドル)を回復したのは、実に25年後の1954年11月のこと。この長期にわたる停滞と回復の歩みは、投資家にとって「失われた四半世紀」として歴史に刻まれることとなりました。
以下では、この25年間に起きた歴史的出来事と、その中での市場の反応を時系列でたどりながら、“時間こそが最大のリスク” だった時代を振り返ります。
【主な出来事】
・1929年:株式市場の大暴落 (ブラックマンデー)
10月の「ブラックサーズデー」「ブラックマンデー」などの連続暴落により、ダウ平均はピークの381ドルからわずか2年で約89%下落(1932年に41ドルを記録)。
・1930年代:世界大恐慌
銀行の取り付け騒ぎ、大量失業(失業率25%超)、企業の倒産、農業価格の暴落などにより、米経済は長期の収縮へ。
・1933年:ニューディール政策開始
フランクリン・D・ルーズベルト大統領が就任し、公共事業(WPA)、預金保険(FDIC)、証券取引委員会(SEC)創設などを実施。金融インフラが整備され、最悪期を脱出。
・1939年~1945年:第二次世界大戦
戦時経済により雇用と産業が急回復。大量の軍需生産と政府支出が経済を刺激し、景気回復の大きな契機となった。
【市場動向】
・記録的暴落の後、10年以上にわたり停滞期が続く。
ダウ平均は1932年に底を打った後も不安定な動きが続き、1937年のリセッションで再び20%以上下落するなど、持続的な上昇には至らなかった。
・1940年代後半から安定成長モードに移行。
第二次世界大戦による軍需景気と、戦後のGI法による住宅建設・教育投資などが需要を押し上げ、株価もようやく本格上昇を開始。
・1929年の高値(約381ドル)を回復したのは、1954年11月23日。
これ史上最も長く続いた市場の「高値回復待ち期間」として記録されており、回復までに25年を要したことから「失われた四半世紀」とも呼ばれています。
・ニューディール政策は直接的な株高をもたらさなかったが、制度的安定を築いた。
証券取引の透明性や預金保護制度の導入は、資本市場の信頼回復と再建に寄与した点で、非常に重要な役割を果たしました。
1966年~1982年(回復期間:16年)
1966年から1982年の16年間は、名目上は成長が続いていたにもかかわらず、実質的には投資家の購買力が大きく削がれた「見えにくい失われた時代」でした。
この時期、アメリカ社会は激動の只中にありました。ベトナム戦争の泥沼化によって国内は政治的・社会的に分断され、戦費による財政負担がインフレの火種となりました。
1971年には、ニクソン大統領が金とドルの交換を停止し、第二次世界大戦後の国際通貨体制であったブレトン・ウッズ体制が崩壊。これによりドルは変動相場制へと移行し、通貨不安と物価上昇が加速していきます。
さらに1973年と1979年に立て続けに発生したオイルショックは、エネルギーコストの急騰と供給不安を引き起こし、企業収益と消費を圧迫。これらの背景のもと、アメリカ経済は「スタグフレーション(景気停滞とインフレの同時進行)」という未曾有の状況に突入しました。
この混迷の時代に、株式市場も例外ではありませんでした。ダウ平均株価は1966年に1,000ドルを突破したものの、以降16年にわたってこの水準を一度も明確に上回れず、投資家は表面上の成長とは裏腹に、実質的な価値の減少と闘い続けることとなりました。
以下では、この時代を象徴する経済・政策・市場の動向を振り返りつつ、なぜこの期間が「投資家にとって最も困難な時代の一つ」とされるのかを見ていきます。
【主な出来事】
・ベトナム戦争(1965年〜1975年)
戦費拡大による財政悪化とインフレ圧力。国内の政治的不安・社会的分断も強まり、市場心理は低調に。
・1971年:ニクソン・ショック
大統領リチャード・ニクソンがドルと金の交換停止を発表。ブレトン・ウッズ体制が崩壊し、為替は変動相場制へ移行。ドルは不安定化し、輸入物価上昇→インフレ加速。
・1973年・1979年:2度のオイルショック
OPECによる原油供給制限で原油価格が急騰。1973年には原油価格が4倍になり、エネルギー価格の急上昇が企業利益と消費者支出を圧迫。1979年はイラン革命が引き金となった。
・1970年代:スタグフレーション(インフレ+不況)
通常、景気悪化時は物価が下がるが、この時期は失業と高インフレが同時に進行。経済政策の混乱とFRBの対応の遅れが状況を悪化させた。
【市場動向】
・ダウ平均株価は「名目」ではほぼ横ばい、実質では大幅下落
1966年にダウ平均は約1000ドルに到達したが、その後1982年まで一度もこの水準を明確に超えることができなかった。一方で消費者物価指数(CPI)は同期間に2倍以上に上昇しており、実質的な株式リターンはマイナスであった。
・S&P500のインフレ調整後リターン:−60%超(1966〜1982)
資産インフレや利上げの影響で、債券市場も低調だった。株式・債券両方が苦しい「金融的冬の時代」だった。
・金利の高騰と株式バリュエーションの圧縮
1981年には政策金利が20%(ボルカーショック)に達し、PER(株価収益率)も歴史的低水準に。投資家のリスクプレミアムが最大化された局面。
・インフレ連動の現物資産(金・不動産)に資金が流れた時代
金は1971年〜1980年で価格が約20倍に。不動産や商品先物市場に関心が移ったことも、株式市場の低迷に拍車をかけた。
2000年~2013年(回復期間:13年)
2000年から2013年にかけての13年間は、株式市場にとって「二度の大規模バブル崩壊と、グローバル金融秩序の再構築を強いられた激動の時代」でした。
表面的な価格は戻っても、実質的な資産形成の停滞と心理的後遺症が残る期間であり、ポートフォリオの多様性・リスク管理・金融政策の影響力など、現代の投資戦略にとって多くの教訓を残した時期でもあります。
【主な出来事】
・2000年:ドットコム・バブル崩壊
インターネット関連企業への過剰投資と過大評価が一気に崩壊。ナスダックはピークから約78%下落、S&P500も2002年にはピークから約50%下落。多くのIT企業が倒産・再編され、Tech Winter と呼ばれる時代が訪れた。
・2001年:9.11米同時多発テロ
米国本土への大規模テロ攻撃は、世界中の金融市場に深刻な不安をもたらし、投資家心理を冷却。航空・旅行・金融セクターを中心に株価が急落し、FRBは利下げで対応したが、回復には時間を要した。
・2008年:リーマンショック(世界金融危機)
サブプライム住宅ローンを発端とした信用バブルの崩壊により、リーマン・ブラザーズが破綻。グローバルな金融システムが麻痺し、株式市場は世界的に暴落。S&P500は2007年の高値から2009年にかけて57%以上下落した。
【市場動向】
・10年足らずの間に2度の「50%級の暴落」
2000年と2008年に発生した暴落は、それぞれハイテクバブルとクレジットバブルに起因。いずれも投資家の信頼を深く損ない、長期投資のリターンが消滅する「ロスト・デケード(失われた10年)」を形成した。
・名目株価の回復に13年を要した
S&P500は2000年3月に1527の高値を記録したが、その水準を明確に上回ったのは2013年3月(過去最高値更新)。これは1929年~1954年、1966年~1982年に次ぐ「歴史上3番目に長い回復期間」だった。
・インフレ調整後の実質リターンはゼロ〜マイナス圏
米国投資家の実質購買力は、13年間ほぼ横ばいか、場合によっては目減りしていた。特に退職直前の団塊世代には痛烈な影響があった。
・金融政策の転換点:QE時代の幕開け
FRBは2008年以降、ゼロ金利政策(ZIRP)と量的緩和(QE)を断続的に実施。これにより市場は徐々に安定を取り戻し、2013年以降はS&P500が長期的なブルマーケットに突入することとなる。
現在、2025年はどこに位置する?
2025年4月現在、AIブームはトランプ関税がもたらす世界経済の不確実性とともに転換点を迎えています。AIブームの先導株であるNVIDIA(NVDA)は、過去最高値から約37%下落し、先導株の座はAIソフトウェアの Palantir(PLTR)に移行しています。
更に米株のバリュエーションに対する懸念が高まりつつあります。トランプ大統領による関税政策が、世界経済の不確実性を一層高めています。
これらの政策が影響を及ぼすには時差があり、企業のコスト増加や消費者物価の上昇を招き、インフレ圧力を強めることが予想されます。このような状況は、過去の歴史的な停滞期と類似しています。
例えば、1970年代のスタグフレーション期には、原油価格の急騰や高インフレが経済成長を阻害しました。また、1929年の大恐慌後の回復には25年を要し、2000年のドットコムバブル崩壊後も、持続的な成長の再開には10年以上かかりました。
現在の状況も、これらの歴史的な停滞期と同様に、資産バブルの崩壊、政策の不確実性、地政学的な緊張などが重なり合い、長期的な経済停滞のリスクを高めています。
停滞期から学ぶ教訓
株式市場には長期的な上昇トレンドが存在する一方で、数十年単位の「停滞期」がたびたび出現してきました。これは単なる景気循環ではなく、経済の構造自体が揺らぐようなマクロ要因によって引き起こされるのが特徴です。
停滞期を引き起こす主な原因
■ 資産バブルの崩壊
– 1929年:株式投機バブルの崩壊(大恐慌)
– 2000年:ドットコム・バブルの崩壊
– 2008年:信用バブルとサブプライム危機の崩壊
いずれも、過剰な信用拡大や将来成長への過信によって資産価格が膨張し、それが崩壊することで市場は深刻な調整局面に入ります。
■ 経済・制度の構造的な変化
– 1930年代:金本位制の終焉、ニューディール政策導入
– 1971年:ニクソンショックによるドルと金の切り離し
– 戦争:第一次・第二次世界大戦、冷戦、ベトナム戦争
制度・通貨・地政学的枠組みの再構築は、企業や投資家の意思決定を不安定化させ、長期にわたる市場の低迷を招きます。
■ 高インフレ・地政学的な不安定
– 1970年代:オイルショック、スタグフレーション、米ソ対立
インフレと失業が同時に進行するスタグフレーションは、経済の根本的な治療なしには抜け出せない構造的困難を生みます。
停滞期からの脱却に必要な要因
■ 生産性の大幅な向上
– 戦後の製造業革命(自動車、電化、住宅建設)
– 2000年代以降のIT・クラウド・AIによる効率化
技術革新による全体の生産性向上が、「持続的な利益成長の再始動」を後押しします。
■ 政策の大改革
– 1933年:FDRのニューディール政策
– 1980年代:ポール・ボルカーによる20%金利でのインフレ退治
– 2008年以降:FRBの量的緩和とゼロ金利政策
危機対応にとどまらず、制度・通貨・中央銀行政策の刷新が市場再建の土台となります。
■ 技術革命による経済構造の刷新
– 第二次大戦後:自動車・航空・家電
– 2010年代以降:スマートフォン、クラウド、AI、EV
新しい産業が雇用・需要・資本投下の主役となることで、投資家心理と企業利益が新たな成長軌道に乗ります。
まとめ
過去100年の市場を振り返ると、大きな上昇期の裏には、かならず長い停滞と混乱の時代が存在していました。それは単なる価格調整ではなく、時に制度そのものが揺らぎ、資本主義の根幹が問われる局面でした。
しかしその一方で、市場は必ず新たな成長の種を見出し、構造を作り直しながら回復してきたのもまた事実です。したがって、投資家がこのような停滞期から学ぶべき最大の教訓は、「単なる価格の動きではなく、背後にある構造変化に目を向けること」かもしれません。