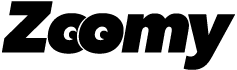GMOの共同創設者、バブルハンターとして知られるジェレミー・グランサム氏の貴重な「人口動態の変化」を見つめた洞察をご紹介します。以下のグランサム氏のスーパーバブル記事と合わせてお読み下さい。
人口動態の変化
私が最近注目しているのは「人口動態の変化」です。ジャーナリズムの世界では「人口動態について書いてはいけない」と言われることがあります。それは、人口動態の分析を一度行ってしまうと、すべての答えが明確になり、それ以上書くことがなくなってしまうからです。
しかし、人口の変化を理解することは、将来を予測する上で極めて重要です。私は今、この変化が市場や経済にどのような影響を与えるのかを考えています。人口の動向を見れば、未来の経済の方向性をある程度予測することができます。
私はジャーナリズムの世界では「人口動態について書いてはいけない」という暗黙のルールがあるとは知りませんでしたが、金融の世界でも同様の傾向があることに気付きました。
私は25年間、一定の読者層を持ち、四半期ごとのレターを書いてきましたが、初めて書いた人口動態に関する論文は、まったく反応がありませんでした。これは非常に時間と労力をかけた研究だったにもかかわらず、まるでブラックホールに消えたかのようでした。
この無反応にはしばらく落ち込みましたが、やがて気付きました。人々は「人口減少」というテーマを聞きたくないのです。人口が減少する理由、その影響、そしてそれが未来に何をもたらすのか。これらは人々を不安にさせるため、避けたい話題なのです。
労働力の減少は経済にとって非常に悪いニュース
しかし、私は人口減少こそが、最も深刻で急速に進行する潜在的な脅威だと考えています。この問題を短期的な視点で理解してもらうためには、こう伝えるべきでしょう。「労働力の減少は経済にとって非常に悪いニュースだ」と。
労働時間の減少は、GDPの成長率に直結します。例えば、私が1960年代にアメリカに移住した当時、労働力の成長率は年1.5%でした。しかし、過去15年間のヨーロッパでは、労働力成長率がマイナス0.5%に落ち込んでいます。
労働力が減少している国では、生産性も低下している
これはGDP成長率に直結するため、2%もの経済成長の喪失を意味します。さらに、我々はもう一つの重要な点に気付きました。労働力が減少している国では、生産性も低下しているのです。
最近の研究で、労働力の減少と一人当たりの生産性の低下には明確な正の相関があることがわかりました。その相関係数は約0.3で、国ごとにデータをプロットすると、人口が多い国ほど生産性が高い傾向が見えてきます。
しかし、これは直感的に理解しにくいことかもしれません。労働人口が減少すれば、企業は生産性向上を目指すべきです。
実際、イギリスでは長年にわたって「生産性向上」の議論が続いており、特に移民政策が緩和されたことが労働力の安価な供給を可能にし、その結果として生産性が伸び悩んだのではないかとも考えられています。
もし労働市場が引き締まり、人件費が上昇すれば、生産性が向上するのではないか、という議論もあります。しかし、経済は単純なメカニズムではありません。確かに、特定の状況下では労働市場が引き締まることで生産性が向上する可能性もあります。
「アニマル・スピリット(投資意欲)」の喪失
しかし、私が考える生産性低下の主な原因は、「アニマル・スピリット(投資意欲)」の喪失です。子どもが減り、幼稚園や小学校が閉鎖され、大学の志願者数が減少していく社会では、人々の意識にも変化が生じます。
企業も成長機会を見いだしにくくなり、昇進のペースは鈍化し、従業員の意欲も低下します。こうした状況下では、企業は資本投資を抑え、ベンチャーキャピタルへの関心も薄れていきます。
なぜ成長している経済の方が活力があるのか、それは経済全体が拡大する中で、より多くのチャンスが生まれるからです。しかし、縮小していく経済では、企業は適応に苦しみ、成長を前提とした経営から、縮小に対応するための難しい舵取りを求められます。
デトロイトの自動車産業や、日本の長期停滞
デトロイトの自動車産業や、日本の長期停滞を経験した企業に話を聞けば、その苦労がよく分かるでしょう。成長する経済を運営するのは、資本主義の得意分野です。しかし、衰退する経済を運営するのは、はるかに難しいのです。
例えば、10軒の店があるうち4軒が閉店したとしたら、残りの6軒の状況はどうなるでしょうか?どの業界でも、供給過剰によって企業が倒産に追い込まれると、利益率に悪影響が及びます。
市場に過剰なキャパシティがあると、利益を確保するのが難しくなり、生き残りをかけた企業同士の競争が激化します。その結果、業界全体が苦しむことになるのです。
鉄道駅を閉鎖することを考えてみてください。それを円滑に縮小するのは非常に困難です。このような状況では、社会全体が楽観的なムードにはなりません。むしろ、人々は失望し、社会全体の士気が低下します。
アメリカでも、楽観的だった社会が急速に不満を募らせていく様子が見られました。人々が失望すると、不満を持つようになり、結果として与党への反発が強まります。ここ数年、ヨーロッパではこの傾向が顕著で、左右を問わず与党が次々と退陣に追い込まれています。
社会の不安定さは、生産性の低下を引き起こし、経済全体に悪影響を及ぼす
実際、バイデン政権への支持率の低下も、過去のヨーロッパ各国の選挙と比べれば比較的穏やかなものでした。このような社会の不安定さは、生産性の低下を引き起こし、経済全体に悪影響を及ぼします。
ケインズは、「どれほど経済刺激策を講じたとしても、人々が悲観的になり、消費を控えるようになれば、景気後退や恐慌に陥る」と述べています。つまり、経済政策がどれほど優れていても、社会の心理状態が冷え込めば、経済は停滞してしまうのです。
では、この状況はどの程度修正可能なのでしょうか?ヨーロッパでは人口が減少し、特に出生率の低下が驚くほど速いペースで進行しています。英国も例外ではありません。
長期的な解決策とは?
移民の受け入れによって一時的に人口減少を補うことは可能ですが、それが長期的な解決策になるかは疑問です。多くのヨーロッパ諸国では、大規模な移民受け入れを好意的に受け止めていないのが現状です。
しかし、2100年までの長期的な人口動態予測を見ると、ヨーロッパは必ずしも人口崩壊の危機に直面しているわけではありません。今後75年間で、約2億人の移民が流入し、同じく2億人の自国民が減少すると予測されています。
結果として、人口バランスはある程度保たれる可能性があります。また、移民受け入れに消極的な国々が、労働力不足によって経済的に破綻していくにつれ、移民政策への考え方も変わるでしょう。
各国の政策や学術研究が進むにつれ、移民の必要性がより明確になり、社会的な認識も変化していくと考えられます。問題は、移民の供給源がどこにあるかという点です。現在のペースで進めば、約45年後にはアフリカの出生率も人口置換水準(2.1)に近づくと予測されています。
移民がヨーロッパにとっての解決策となる期間は、おそらく75年程度
つまり、移民がヨーロッパにとっての解決策となる期間は、おそらく75年程度でしょう。しかし、その後は移民の供給自体が減少するため、労働力不足を補う手段としての移民政策は機能しなくなる可能性があります。
出生率は、ほぼすべての国で予想以上に速いペースで低下しています。アフリカの出生率は現在6.5から4.2へと急速に低下しており、このスピードが続けば、予測よりも早く人口置換水準に達するかもしれません。
単に移民を増やすという短期的な解決策
それが40年後なのか50年後なのかは確定できませんが、いずれにせよ、多くの人々が予想しているよりも早くその時が訪れるでしょう。このため、単に移民を増やすという短期的な解決策では、人口減少の問題を根本的に解決することはできません。
長期的に考えれば、どの国もいずれ人口減少に直面し、労働力の移動で問題を解決することが難しくなります。また、英国では「移民も年を取る」という指摘があります。
移民を受け入れ、高齢化した労働力を補うことは短期的な対策になりますが、その移民世代もまた高齢化するため、問題の根本的な解決にはなりません。結局のところ、移民を受け入れることで時間を稼ぐことはできますが、その間に人口減少の根本的な解決策を見出す必要があります。
人口減少には、二つの問題がある
人口減少には、二つの問題があります。一つは、我々が「有害な環境」を作り出した結果として、出生率が低下しているという事実です。特にこの15年間でその傾向が顕著になり、今後も続くと考えられます。この問題に対する合理的な解決策は、今のところ見当たりません。
長期的に見れば、移民政策だけでは人口減少を克服することはできず、新たな戦略が必要になるでしょう。最終的には、社会全体がどのように適応していくかが鍵となります。
私たちは、地球環境を十分な速さで改善し、危機を防ぐことができるでしょうか?それには数十年かかるかもしれませんが、一部の地域、例えばEUのように環境対策が進んでいる場所では、最終的にある程度のブレーキがかかるでしょう。
プロパガンダ的な有害資本主義
しかし、もう一つの大きな問題として、私は「プロパガンダ的な有害資本主義」とでも呼ぶべき現象があると考えています。現代社会では、子どもを持つことに対するネガティブな文化が広がっています。
何らかの理由で、子どもを持たないほうが個人にとって有利だと考えられるようになり、それを助長するインセンティブが与えられています。その結果、多くの人が「より良い人生」を求めて子どもを持たない、あるいは少ない子どもしか持たなくなっているのです。
しかし、出生率を変えるには、社会全体のインセンティブを変える必要があります。私の予想では、数十年以内に、文化的な価値観を「家族を大切にし、健康で十分な教育を受けた2.1人の子どもを育てること」を社会の共通の目標とする方向へ転換しなければならなくなるでしょう。
コモンズ(共有財)
これは社会の「コモンズ(共有財)」の一部として考えられるべきものです。なぜなら、もし平均出生率が2.1人を下回り続ければ、人類は驚くほどの速さで減少し、存続の危機に直面するからです。データを見れば、そのスピードがいかに速いかが分かるでしょう。
清潔な空気、健康な土壌、きれいな水が必要不可欠であるのと同じように、2.1人の健康で教育を受けた子どもが社会には必要です。そして、そのための仕組みを作ることが求められています。
「私たちの家庭は1.9人しか子どもがいないから、私は少し罪悪感を感じます。」
「それなら、うちは2.3人だから、ちょうどバランスが取れていますね。」
こうした冗談を交わしながらも、私たちは本質的な解決策を提示できているわけではありません。最終的には、社会全体の生き方を変えていく必要があります。
この問題の解決は、まず人々の意識を変えることから始まります。どんな政策よりも、まず99%の人々に「問題が何なのか」を理解させなければなりません。しかし、現状では、そもそもこの話を聞こうとする人がほとんどいません。
その間にも時間は刻一刻と過ぎていきます。私たちは、「これは深刻な問題であり、解決可能である」と人々を説得し、インセンティブの設計を変えなければなりません。
中国では、間違いなく政府が厳しい手法を取り始めるでしょう。例えば、「結婚しないと住宅を購入できない」といった政策を導入するかもしれません。
また、インセンティブとして、単なる6,000ドルの給付ではなく、子ども1人につき8万ドルの支援を提供する、保育を全面的に補助する、教育費や医療費を無料化する、といった大胆な施策が必要です。
子どもを持つことは単なる個人の選択ではなく、社会全体の利益につながる
なぜなら、子どもを持つことは単なる個人の選択ではなく、社会全体の利益につながるからです。もちろん、子どもを持たないという選択もできますが、社会全体が人口減少によって崩壊してしまえば、その選択も意味をなさなくなります。
インフラが維持できず、経済が縮小し、生活の質が大幅に低下するからです。したがって、社会全体として「子どもを持つことは価値ある行為である」という文化を作る必要があります。社会全体が子育てを支え、子どもを持つことの意義を再評価することが求められています。