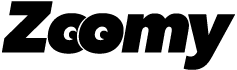2025年2月15日に放送された「情報7daysニュースキャスター」で氷河期世代の特集が話題になっています。同じタイミングで、日本経済新聞の「持ち家なき氷河期世代 賃貸負担重く、老後に困窮リスク」という記事が話題を集めていますので、全体像を分かりやすく解説します。
持ち家なき氷河期世代 賃貸負担重く、老後に困窮リスクhttps://t.co/bTEDNwzcu0
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) February 15, 2025
まずは40代就職氷河期世代の実態を知るには、日本の単身世帯における年代別の「平均貯蓄額」と「中央値」を見てみると、氷河期世代は他の年代に比べると厳しいことが浮き彫りになります。
日本の単身世帯における年代別の平均貯蓄額と中央値
| 年代 | 平均貯蓄額 | 中央値 |
|---|---|---|
| 20代 | 176万円 | 20万円 |
| 30代 | 494万円 | 75万円 |
| 40代 | 657万円 | 53万円 |
| 50代 | 1,048万円 | 53万円 |
| 60代 | 1,305万円 | 300万円 |
| 70代以上 | 1,683万円 | 500万 |
これらのデータは、金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(令和4年)」を基にしています。平均値と中央値の差が大きいことから、一部の高額貯蓄者が平均値を引き上げていることがわかります。
そのため、実態を把握する際には中央値を参考にすることが重要です。これらの数値は、各年代の一般的な傾向を示していますが、個々の状況によって異なる場合があります。
貯蓄計画を立てる際には、自身のライフスタイルや将来の目標に合わせて検討することが大切です。
就職氷河期世代である40代の貯蓄額が少ない
就職氷河期世代である40代の貯蓄額は、他の年代と比較して少ない傾向が見られます。特に、中央値が低いことから、多くの方が十分な貯蓄を持っていない現状が浮き彫りになっています。
この背景には、就職氷河期における厳しい雇用環境が影響しています。当時、多くの大企業が新規採用を抑制したため、希望する職種や企業に就職できなかった方が多く、結果として中小企業や非正規雇用でのキャリアをスタートせざるを得なかったケースが多々ありました。
その後の収入やキャリア形成にも影響を及ぼし、現在の貯蓄額の差となって表れていると考えられます。
就職氷河期世代の約3分の1が非正規雇用
就職氷河期世代の約3分の1が非正規雇用であり、貯蓄がない方も多いとされています。日本FP協会が2023年に実施した調査によれば、38歳から46歳の働く男女1,000人を対象とした結果、世帯の貯蓄・投資総額が「貯蓄・投資はしていない」と回答した割合は15.0%、「50万円未満」が15.8%であり、300万円未満の層が全体の約50%を占めています。
また、別の調査では、40代の貯蓄がない世帯の割合は27.6%と報告されています。このように、就職氷河期世代は非正規雇用の割合が高く、貯蓄が少ない傾向が見られます。
老後の賃貸負担が重荷
就職氷河期世代(現在の40代から50代)は、非正規雇用や低収入の影響で持ち家を持たない方が多く、老後に賃貸住宅の家賃負担が重くのしかかる可能性が指摘されています。
日本総合研究所の報告によれば、非正規雇用者が増加した就職氷河期世代以降では、基礎年金への依存度が高い受給者も増えると予想され、低所得の単身世帯が生活を維持できなくなるリスクが増大すると懸念されています。
また、PRESIDENT Online の記事「このままでは70歳まで働いても生活保護以下」では、就職氷河期世代の中でも特にシングル女性の貧困問題が深刻であり、40年後には約半数が生活保護レベルの収入になる可能性があると報じられています。
このような状況を踏まえ、政府や自治体は就職氷河期世代への支援策を講じています。
例えば、再就職支援やスキルアップのための研修、生活支援などが提供されています。これらの支援を積極的に活用し、将来の生活設計や資産形成に役立てることが重要です。
残念ながら日本の年金制度も雀の涙ぐらいの足しにしかなりませんので、政府に期待するのではなく、個人での対策が必要になります。
軽視されている健康寿命の問題
老後の備えとしてお金も非常に大切ですが、それ以上に見落とされがちなのが「健康寿命」です。健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく過ごせる期間のことを指します。加齢に伴う身体のダメージが蓄積されることで、人間の老化は進行します。
年齢を重ねるほど、身体への負担が蓄積し、歩行が困難になったり、通院が必要になったりと、これまで健康だったときには想像もしていなかった問題が生じることがあります。
そもそも、ある程度健康を維持できなければ、働くことすら難しくなり、収入が途絶えてしまう可能性があります。さらに、慢性的な疾患を抱えると、治療費がかさむだけでなく、治療にかかる時間も奪われてしまいます。
歩行が困難になったとき、十分な蓄えがなければ路頭に迷ってしまいます。このことからも、健康を維持することは、老後の生活を守るためにも非常に重要なのです。
【関連記事】選書『Why We Die 私たちはなぜ死ぬのか?老化と不死の謎に迫る』
個人での資産形成「積立投資」が鍵になる
以上のことを考慮すると、頼れるのは自分だけです。人生100年時代というのは言い過ぎだと思いますが、今の日本人なら80歳前後までは生きるものだと仮定します。そうすると後半分の時間が残っています。
また超高齢化社会を迎えている日本では、40代でも貴重な労働源であり、仕事さえ選ばなければ働き口はあるかもしれません。そう考えると節約生活をして、個人での資産形成「積立投資、インデックス投資」が40代就職氷河期世代の生存戦略となります。
「積立投資」の基本概念は時間を味方に付け、複利の力で資産を形成するというものです。やっている人は、20代/30代からこの積立投資を開始しています。
この記事を書いている私も30代から積立投資を開始し、2025年2月現在金融資産は倍になっています。”投資” と聞くと「私には無理 …」と思う方もいるかもしれませんが、欧米に比べると日本人は金融知識に乏しいので無理もありません。
私も当初は自分に “投資” なんてできるのかな?と不安に思っていましたが、フリーランスの身でしたので未来への不安から、「積立投資、インデックス投資」に関する勉強を始め、徐々に金融知識を独学で猛勉強しました。まずは未来への不安に対して、覚悟を持って学ぶ姿勢が必要です。
それでも「私にはできない …」と思う方がいるかもしれませんが、誰にでもできます。アメリカには、生涯をガソリンスタンドの店員/清掃員として働いた、ロナルド・ジェームス・リードという人物がいます。
彼はいわゆるブルーカラーであり、日本で言えば非正規のようなものです。家族で初めて高校を卒業しました。第二次世界大戦中、イタリアで憲兵として従軍した後、バーモント州ブラトルボロに戻り、ガソリンスタンドで25年、その後J.C.ペニーで清掃員として17年働きました。
リードさんは2014年に92歳で亡くなりましたが、その時の純資産は800万ドル以上 (日本円で現在だと12億) にもなっていました。彼が行った投資戦略は非常にシンプルなものでした。それは、日々働き、節約したお金をインデックス・ファンドに投資し続けることでした。
リードさんと私たちが生きている時代では状況は大きく異なりますが、それでも「節約して積立投資 (インデックス投資) を続ける、時間を味方につけて複利の効果で資産を増やす」というのは非常にインパクトがあることだというのが理解できるはずです。
【関連記事】積立投資の大原則「複利の力、複利の効果」を学ぼう
チューリッヒ工科大学の企業家リスク名誉教授ディディエ・ソルネット氏は、「金融が世界を動かしているため、その本質を理解することが重要です。そうでなければ、あなた方は羊であり、搾取されることになるからです。」と語っています。
金融と言っても、まずは「積立投資、インデックス投資」の原理・哲学を理解し、個人でネットで証券口座を開設し積立投資を開始するのがスタートとなります。その中で経済がどのように回っているのか?を積立投資をしながら常に学ぶ姿勢が求められると思います。
40歳から積立投資を始めるのは遅い … という声もあるかもしれませんが、そんなことは言ってられないのと、巷では『40歳からの〇〇投資』というような本も多く出回っているようです。
単純に見積もって、40歳から20年投資を続けても60歳です。まだまだ間に合うはずです。