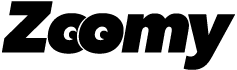「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げた大阪・関西万博2025が、25年4月13日にいよいよ開幕しました。大阪万博2025と言えば、開幕前には、SNS上での批判や懸念の声が数多く見られました。
大阪・関西万博2025は開催に至るまでの道のりで多くの課題に直面しました。着工の大幅な遅れや、世界的なインフレーションによる建設費の高騰は、事業の実現可能性自体を疑問視する声を生みました。
また、公式キャラクター「ミャクミャク」のデザインに対しては「不気味」「理解不能」といった厳しい批判が相次ぎ、SNS上では否定的な意見が圧倒的多数を占めていた。
メディア報道も問題点や懸念事項を中心に伝えることが多く、開幕直前まで「失敗に終わるのではないか」という悲観的な見方が支配的だった。開催への期待感より不安や批判が先行し、ポジティブな意見はほとんど見られない状況でした。
ところが万博が実際に開幕すると、状況は一変しました。開場初日から予想を上回る入場者数を記録し、各パビリオンの革新的な展示に対する称賛の声がSNS上で急速に広がり始めました。
特に注目すべきは、かつて批判の的だった公式キャラクター「ミャクミャク」のキャラクターグッズが公式のオンラインショップで、ぬいぐるみやフィギアが開幕初日に完売したことです。
なぜこのような総批判されていた大阪・関西万博2025が、開幕と同時にその機運が高まり世間の関心を集めているのか?を考察したいと思います。
大阪万博開催前の渦巻くネガティブな意見
開幕前の大阪・関西万博2025は、様々な批判に包まれていました。その多くは建設工事の大幅な遅延や予算超過問題、そして公式キャラクター「ミャクミャク」のデザインへの違和感など、限られた情報やイメージに基づく批判でした。
SNS上では否定的な意見が連鎖的に拡散され、万博に対する社会的評価は極めて厳しいものとなっていました。しかし、実際に万博が始まり、万博のテストランで完成した会場が報道されたり、万博開幕直前の特集が組まれるなど、万博の開催が迫ると少しずつ大阪・関西万博2025への機運が高まってきたように感じました。
特に開催の前日にNHKで生放送された、万博直前の特集番組では、芸能人やアイドルなどが万博会場から万博の魅力を伝え、ちょっと行ってみたい、気になる!というような盛り上がりを感じました。
そして25年4月13日、大阪・関西万博2025が遂に開幕し、来場者が現地での体験を通じてその魅力を感じることで、評価が大きく変化しました。この現象は、情報だけでは体験の価値を完全に伝えることができないという事実と、実体験がいかに人々の認識を変え得るかを示す興味深い事例だと思います。
期待値と現実のギャップによる「認知的不協和」
開催前のネガティブな報道やSNSでの批判の連鎖により、多くの人々は大阪・関西万博2025に対して著しく低い期待値を形成していました。
しかし、実際に万博が始まり、予想以上の内容や盛り上がりを目の当たりにすると、当初の期待と現実とのギャップにより「認知的不協和」が生じます。この不協和を解消するために、人々は自分の認識を修正し、万博を肯定的に捉えるようになるのです。
人は最初にネガティブな情報ばかりを見聞きしていると、それが基準になります。しかし、実際に体験したり、見たりした際に「意外と良い」、「思ったより面白い」と感じると、そのギャップがポジティブな感情を増幅させます。
認知的不協和とは、人が持つ二つの矛盾した認識や信念が存在する時に生じる心理的不快感を指します。「万博はつまらないはずだ」という事前認識と「実際には面白い」という体験の間の矛盾が、来場者や情報を受け取る人々に心理的な不快感をもたらします。
この不協和を解消するために、人々は自然と自分の認識を修正する傾向があります。「思ったより良かった」という評価はまさにこの認知の修正プロセスであり、予想外の良さを強調することで認知的整合性を取り戻そうとする心理メカニズムの表れなのです。
特に興味深いのは、事前の期待値が低ければ低いほど、実際の体験との落差が大きくなり、その結果としてのポジティブ評価も増幅される点です。「最悪だと思っていたのに意外と良かった」という評価は、「普通に良い」という評価よりも強い印象を残し、口コミやSNSでの拡散力も高まります。
SNSを通じたポジティブな意見の拡散
開幕後、実際に万博を訪れた人々がSNSやブログでその魅力を発信し、ポジティブな情報が広がっていきました。ご存知の通り、万博開催前は120%のネガティブな意見が渦巻いており、これ以上下がりようがないという所まで、今回の大阪万博のイメージは地に落ちていました。
つまり落ちる所まで落ちた大阪万博のイメージが、開幕して一転、実際に訪れた人のポジティブな意見 (実際に行ったら感動した) に、当初の否定的なイメージが払拭され、訪れた人の声を聞いて自分も行ってみたい!面白そう!!
というような多くの人々の関心を引きつけています。
周囲の反応に影響される「バンドワゴン効果」
これには「バンドワゴン効果」の影響もあるはずです。万博が始まり、メディアでの好意的な報道やSNSでのポジティブな投稿が増えると、それに影響されて「自分も行ってみよう」と考える人が増えます。
これは「バンドワゴン効果」と呼ばれ、多くの人が支持しているものに対して、自分も支持しようとする心理です。この効果により、当初はSNSの空気に流れてしまい関心がなかった人々も万博に興味を持ち、来場者数の増加につながったと考えられます。
日本人特有の「お祭り気質」
祭り好きな日本人の文化的性格も、今回の万博への評価が一転したことに影響していると思います。日本には、普段の慎ましい日常(=ケ)から一転、非日常的な祝祭空間(=ハレ)で思いっきり騒ぐという伝統文化があります。
万博のような大型イベントは、まさにこの「ハレ」の時間。普段は冷ややかでも、始まった途端に空気が変わるのは自然なことです。日本人は空気を読む(=KYじゃいけない)という文化の中で育っており、周囲の盛り上がりに自然と同調する傾向があります。
一種の「祝祭モード」に社会全体がスイッチすると、それに乗らなきゃ損という感覚が働きます。「万博なんてクソ」と思っていた人でも、実際にグッズを買ったり現地に行ったり、SNSで話題にしたりすることで当事者意識が芽生えます。
これは、「批評する側」から「参加する側」への心理的転換です。
公式キャラ「ミャクミャク」の再評価
日本のお家芸になりつつある大きなイベントの公式キャラクター批判ですが、今回の万博でも公式キャラクターの「ミャクミャク」が酷評され続けました。「気持ち悪い」、「理解不能」、「何でこんなキャラが選ばれたの?」など …
しかし、開幕前の万博のイメージと同様に、実際に万博が始まると初日だけで公式オンラインショップで「ミャクミャク」のキャラクターグッズのぬいぐるみ、フィギアなどがソールドアウトしました。
公式オンラインショップですので、万博に行っていない人が買っており、話題性を狙った転売目的などもあると思いますが、それにしても完売するというのは、当初の「ミャクミャク」の酷評からは考えられない事態だと思います。
この背景にも、万博同様に地に落ちた「ミャクミャク」の後は上に上がるしかない再評価が始まっていると思います。公式キャラの「ミャクミャク」は、35億年前に誕生した、細胞と水がひとつになったことで生まれた、ふしぎな生き物。
6つの目で過去や未来を見ることができるという設定です。万博前の3月には、NHKでミャクミャクがアニメ化され『はーい!ミャクミャクです』というショートのアニメーションが公開されています。
これを見た個人的な感想ですが、実はミャクミャク結構かわいい、愛嬌がある、実はポップ … というような印象を受けた。万博開幕で機運が高まると同時に、公式キャラであるミャクミャクが再評価されているように感じました。
まとめ : 逆転のブランディング
以上のように、今回の現象は、東京五輪の開会式やジブリパークの初動と似た構造を持っており、「始まってみないとわからない」というリアルな体験の力を示しています。
この記事を書いています (25年4月14日現在) 万博は開幕したばかりですが、今回の大阪・関西万博2025は、当初の期待を裏切るのではなく、上回る力を見せており、正に逆転のブランディングと言えるでしょう。
大阪万博2025のブランディングは、初期のネガティブイメージを覆した “逆転劇” として見ることができます。しかし、それは単なる偶然ではなく、
・現地体験 (大屋根リングの壮大さなど) による期待値の上方修正
・SNSを通じた共感の拡張
・公式キャラの再評価
・非日常(祭り)への文化的親和性
といった、社会心理に深く根ざした設計と偶然の連鎖の産物です。私たちは時に、批判し、疑い、冷めた目で未来を眺めてしまいます。しかし、実際に足を運び、体験し、誰かと共有することで、評価は大きく変わるものです。
大阪万博2025と公式キャラのミャクミャクが示したのは、「期待を裏切る」のではなく、「期待を上回る」ことの力。そして、それを可能にしたのが、何とか開幕に漕ぎ着けた関係者の意地、ソーシャルな共鳴、日本人の祭り魂だったのかもしれません。