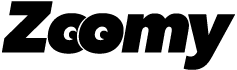日本の年金制度は、日本の人口動態、主に少子高齢化の要因により、将来的に給付額の減少や受給開始年齢の引き上げが予想されています。
少子超高齢化社会
日本は世界でも有数の (世界一) 高齢化社会であり、出生率の低下と平均寿命の延びにより、高齢者の割合が増加しています。これにより、年金受給者が増加し、現役世代の負担が増大しています。
イーロン・マスク氏は過去に日本の出生率低下に対して深い懸念を示しています。彼は、2022年5月当時 Twitter で「出生率が死亡率を上回るような変化がない限り、日本はいずれ存在しなくなるだろう」とツイートしました。
この発言は、日本の急速な人口減少と少子高齢化に対する警鐘として受け取られています。日本の出生数は年々減少しており、2022年には初めて80万人を下回りました。
この傾向が続くと、将来的に労働力の不足や社会保障制度の維持が困難になる可能性があります。マスク氏の指摘は、こうした人口動態の変化が日本の存続に深刻な影響を及ぼす可能性があることを強調しています。
また、マスク氏は世界全体の出生率低下にも懸念を示しており、2021年12月のウォール・ストリート・ジャーナルの年次CEOサミットでは、「もし人々がもっと子供を産まなければ、文明は崩壊する」とも述べています。
年金給付額の減少
2024年の年金財政検証によると、経済成長が低迷するシナリオでは、2044年度に所得代替率が50%を下回り、2052年度には公的年金の積立金が枯渇する可能性が示されています。
この場合、所得代替率は36~38%まで低下し、例えば現在20万円の年金が12万円程度に減少することを意味します。
受給開始年齢の引き上げ
2022年4月の年金制度改正により、老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。 これにより、受給開始を遅らせることで年金額を増やす選択肢が広がりましたが、同時に受給開始年齢の引き上げが進行していることを示しています。
年金財政の圧迫
高齢者人口の増加に伴い、年金給付に必要な財源も増加しています。しかし、労働人口の減少や経済成長の停滞により、年金保険料の収入は伸び悩んでいます。この結果、年金財政のバランスを保つために、給付額の削減や受給開始年齢の引き上げが検討されています。
70歳を過ぎても働く必要がある現実
総務省の「労働力調査」によると、65歳以上の高齢者の就業率は直近10年間で大幅に上昇しています。特に、60代後半の就業率は約14%ポイント、70代前半では約11%ポイントの上昇が見られます。
高齢単身無職世帯の1ヶ月の平均支出は約15.5万円であるのに対し、年金などの平均収入は約13.5万円と、毎月約2万円の不足が生じています。この収入不足を補うため、多くの高齢者が就労を選択しています。
年金だけでは老後に食べていけない多くの高齢者は、70歳、80歳を過ぎても家計のために働いています。これは、長寿化や年金財政の厳しさ、そしてコロナ以降の歴史的なインフレが背景にあります。
更に、政府は高齢者の就労を促進するため、法律の緩和を進めています。例えば、2023年9月からはタクシー運転手が80歳まで働くことが可能となりました。
このように日本では年金だけでは生活が困難な高齢者が増えており、70歳や80歳を超えても働き続ける必要があるのが現実です。
国際的な年金改革の動向
この傾向は日本だけではありません。他の先進国でも、年金制度の持続可能性を確保するために、給付額の見直しや受給開始年齢の引き上げが行われています。
例えば、ドイツやフランスでは、年金受給開始年齢を67歳まで引き上げる改革が進められています。日本もこれらの国際的な動向を参考に、制度改革を検討しています。
年金だけに頼るのは危険
現在、日本の年金制度は少子高齢化の進行や財政状況の悪化により、将来的な給付額の減少や受給開始年齢の引き上げが避けられないと考えられています。これは単なる予測ではなく、政府や専門家による年金財政の検証を通じて、すでに明らかになっている事実です。
例えば、2024年の年金財政検証では、現行制度のままでは将来的に所得代替率(現役世代の収入に対する年金額の割合)が低下し、現在の年金受給者と比べて、将来世代の受給額が大幅に減少する可能性が指摘されています。
さらに、2022年に施行された年金制度改正により、年金の受給開始年齢は70歳まで繰り下げが可能となりました。これは一見、受給者の選択肢を広げるものの、裏を返せば、「65歳で年金を受け取るのではなく、70歳まで働いて受給額を増やさないと、十分な生活費を確保できない可能性がある」ことを示唆しています。
将来的には、年金財源の持続性を維持するために、受給開始年齢が70歳以上に引き上げられる可能性もあり、老後の生活設計を今から真剣に考える必要があります。
こうした状況を踏まえると、「公的年金だけで老後の生活を支えるのは危険である」という認識を持つことが非常に重要です。現在の高齢者世代は、比較的手厚い年金を受け取ることができていますが、現役世代や今後の若年層にとっては、同じような給付が期待できません。
自分年金の積立「新NISA」が急務
したがって、今から積極的に老後資金の準備を行うことが不可欠です。具体的には、自分自身で資産形成を行う「自助努力」が求められます。例えば、「新NISA(少額投資非課税制度)」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」などの制度を活用し、長期的に資産を積み立てていくことが望ましいです。
「新NISA」は、株式や投資信託の運用益が非課税となるため、長期的な資産形成に適しています。一方、「iDeCo」は、自分で積み立てた資金を60歳以降に受け取ることができ、掛け金の全額が所得控除の対象となるため節税メリットも大きく、長期的な資産形成に適しています。
【関連記事】億万長者になった清掃員ロナルド・リードが教えてくれること
メディアは嘘つき
2025年2月3日に放送されたNHKの情報番組『あさイチ』では、「女性の年金が少ない?」というテーマが取り上げられました。番組では、女性の年金額が男性より平均して月額約4万円少ないことが指摘され、その主な要因として、女性の労働期間の短さや賃金の低さが挙げられました。
番組内では、年金分割制度についても関心が寄せられ、「離婚時の年金分割制度を知っておくことが大切だ」との声が紹介されていました。この日の放送は、国会中継があったため、内容もかなり短縮されていたようですが、そもそも論として年金を払ったところで雀の涙だということをちゃんと説明した方が良いでしょう。
もう既に年金だけでは老後の資金が足りないので、年金を払った上で自分年金の形成が非常に大切だということを知らせる必要があったと思います。
健康寿命もキーワード
特に、長寿化が進む日本では、80歳を超えても働くことが必要になるかもしれません。現在、70歳以上の就業率は年々上昇しており、政府も「70歳雇用努力義務」を企業に求めるなど、シニア世代の就労を後押しする動きが進んでいます。
しかし、高齢になってから急に働こうと思っても、体力やスキル面でのハードルが高くなるため、今から長期的なキャリア形成を視野に入れておくことが賢明です。
このように、普通の人程、今から自分年金を形成することが重要です。年金が破綻しないとしても、給付額の減少や受給年齢の引き上げによって、従来の「60歳定年→年金生活」というライフプランは通用しなくなっています。
今後の長い人生を安心して過ごすためには、国に頼るのではなく、自らの力で資産形成やライフプランを構築していく姿勢が強く求められます。
結論
以上のように日本の年金制度は沈みゆく泥舟のようなものです。しかし年金は国民の義務ですので払いましょう。そして年金に頼るのではなく、繰り返しになりますが「自分年金」の積立を直ぐに開始して下さい。